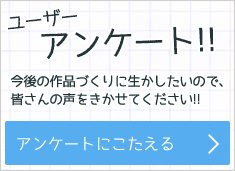ということで、向坂先生の短編小説3/3です!
白愛とは世界観などは違いますが、シナリオのテイストは判ってもらえるかもですね。
爽やか百合で、読後感良い感じです!
し、白愛も爽やかキラ☆ふわガールズラブですけどね・・・(震え声
では最終回!
「海にそそぐ大河のように」
Ⅲ
その時、わたしはもう気力だけで歩いていたので、森がひらけると同時に体に吹きつけてきた心地よい風に、
思わずくらりと膝が崩れそうになった。
そして、ひらけたその草地の真中に立っているのは、小さな寺か何かの古い建物。
「お堂だ!」
音々は言うなり、わたしと組んでいた肩を離して、足を引き摺りながら駆けるようにお堂に近づいていく。
そんな音々を立ち尽くして見ていたわたしは、不意に周りの風景に違和感を覚えた。
木の陰の中に、ぼてっとしたかたまりが幾つも……
音々に追い越されて、彼女を見送るように立ち止まっていた小猫が一声可憐な声で長く鳴いた。
すると、そのかたまりたちがいっせいに起き上がった。
「――猫!?」
そう、そのかたまりは、ぜんぶがぜんぶ猫がうずくまっている姿だったのだ。
あわてて、わたしはお堂の観音開きの扉と格闘している音々のところに駆け寄った。
「あ、ちーちゃん、ちょっと手伝ってよ」
「じゃなくて。ほら、あれ、あれ!」
何にも気付いていない音々をむりやり草地のほうに振り向かせる。
起き上がった猫たちがお堂の前に集まってきていて、さすがに音々も呆気にとられたみたいだった。
なにせ、まるでこの島中の猫が集まってるんじゃないかって思えるくらいの数なのだ。
いくつもの猫の瞳が、わたしたちを――いや、音々一人を、じっと見つめていた。
わたしはふと気付いたのだけれど、音々の真正面の一番前にいる猫の模様が大きな灰色のぶちだ。
音々が話してくれた彼女の旦那さんの血を引いている猫なんだろうか。
いや、もしかすると本人(という表現はおかしいのかな)?
不思議な光景だった。
見つめ合う、猫たちと音々の間には、動作も声も何もなかったけれど、
わたしはなぜかそこに意思の疎通を感じていた。
音々は、懐かしそうに目を細めて、ただいまと静かに言った。
それから、わたしのほうを見て、
「とりあえず、これ開けちゃおうよ」
「この中にあるの? その……」
「そう。この中に、ね」
音々は、確信に満ちた表情をする。
それよりもいいのだろうか。お堂の扉なんか壊して。
そんなわたしの危惧にまるで気付かず、音々は問答無用とばかりに扉を乱暴に開けようとしている。
仕方がない、とわたしも度胸を決めて、音々と一緒に扉に力を込めた。
もうほとんど体に力が入らない状態だったから、わたしは扉に体重をかけるように体を押しつける。
扉の裏側で、何か棒のようなものがへし折れる音がした。続いて、蝶番のきしんだ悲鳴。
思っていたよりもたやすく、勢いよく扉が開いて、わたしと音々はお堂の中に転がり込んだ。
服が、床に溜まっていた塵やら何やらで埃だらけになる。
舞い上がる埃に、わたしと音々は派手に咳き込んだ。
お堂の中にはひやりとした空気が漂っていた。
「うわ、仏像だ……」
身を起こしたわたしは、お堂の奥にあるあぐらをかいたお釈迦様のような像を見てそうつぶやいた。
壁のごく細い隙間から入る明かりを受けて、何だかすごくありがたそうに見えた
(あとで、そういうのは神々しいって言うんだよ、と音々が教えてくれた)。
そして、その膝の上に優しく守られるようにして横たわっているのが。
「……あたしだよ」
音々が言った。
お堂の中の涼しい空気のおかげでか、きれいな白の毛並みの猫の死体は、
腐敗した様子もなくただ干からびていた。
まるで美しさを損なっていない、とはわたしの主観的な意見かも知れないけれど、
でもわたしはそのとき確かにそう感じていた。
「即身仏みたいだよね」
なぜだか、照れくさそうに冗談めかして音々が言った。
即身仏が何かわたしは知らなかったけど、けどきっとそうなんだろうと思ってわたしはうなずいた。
「でも……」
わたしはひとりごとのようにつぶやく。でも、だよ。
「これを見つけてさ。何がどうなるって言うの?」
きれいだなあ、とは思ったけど、わたしにはそこ止まりだ。
音々にしたって、感動の対面というわけでもなさそうだし。
生涯を生き抜いた証なのだとしても、それは、わたしになんの感慨も抱かせはしない。
とくに、なにも。
死体を前にして、普通、人は何を思うものなのかなんて知らないけど。
(生の大切さ?)
わたしは感受性が鈍いのだろうか。
不自然な沈黙の後、音々もひとりごとのように前を向いたままつぶやいた。
「わかんない……」
* * *
「結局、無意味だったなあ」
ぽつりと、音々が言った。
お堂の縁側に並んで座っているわたしと音々の体に、生暖かい風が絡みつく。
今の時期、陽の出ている時間帯はかなり長くなっているのだけれど、さすがにそろそろ薄暗くなってきている。
お堂の軒先のわずかに開いた草地には、猫たちが気持ち良さそうに好きな格好で寝そべっている。
猫だから耳もいいんだろうけど、音々の言葉に反応する猫はいなかった。
まだ青さを残している空にも、薄く月が見える。
「無意味って?」
落ち着いた途端疲れがどっと出て、ぼうっとしていたせいで、かなり遅れてわたしは聞いた。
けれど、その必要はなかったのだった。
音々はわたしに何か伝えたくて、わたしをこの離れ島に連れてきたみたいだけど、
それが結局無意味だったと言いたいんだろう。
音々は、振り返ってお堂の奥の仏像を見つめていた。
それとも、その膝の上の自分の死体を見ているのだろうか。
――ミイラってね、漢字で「木乃伊」って書くんだよ。 音々が、埃の浮いた縁側の木の板に指を走らせた。
変なこと言い出すなあこの子って思ったけど、わたしは黙っていた。
けど、それから音々が言ったセリフはもっともっと変で、わたしは無言を保っていられなかった。
「でもね。あたし、分かったんだ。ちーちゃんに、とことんめーわくかけちやえばいいんだって。
ちーちゃんのことなんか考えないでさ、あたしの自分勝手な都合でちーちゃんには生きててもらおうってね」
「はあ? なによ、それ」
「だってさ、あたしのハッピーライフには、ちーちゃんが絶対欠かせないんだもん。
だからさ、ちーちゃんの事情なんか関係ないよ。とにかく死んじゃ駄目、ちーちゃんは。
なんたって、あたしが困る。あたしの人生台無しだよ、そんなことになったら」
一気に言ってのけた音々に、わたしはしばらくの間呆気にとられていた。
「……わ、わがままなやつぅー!」
「ふん。そうだよ、あたし我儘にはちょっと自信あるもん」
えらそうに胸を張る音々に、わたしは無性におかしくなって、けたけたと笑いころげた。
「何だか、いいよね、そういうのって」
わたしの目には、笑い過ぎで涙が浮かんでいた。
「音々らしくっていいよ、すっごく」
ちゃかすようにわたしは言ったのだけれど、本当はすごく嬉しかった。
わたしという人間が、わたしの好きな人の中でとっても重たい存在になっているんだなあってのは、
すごく嬉しいことだ。
音々は、本当だよ、死んじゃうなんて許さないからね、ちーちゃん! って何度も繰り返して言う。
なんだよ、わたしは音々のものじゃないんだぜってわたしが言うと、音々ったら、そん
なことないよ、ちーちゃんなんかあたしのものだよ! なんて滅裂なこと言ってる。
わたしは、そんなふうにむきになる音々がおかしくって、肺が苦しくなるまで笑い続けていた。
騒いで火照った体には、ぬるい夜風と言えども心地よかった。
疲れたわたしたちは、肩同士もたれあうようにして、猫たちを眺めている。
かなり大きな声で騒いでいたのに、やっぱり猫たちは身動きすることもなく、
まるで風景にとけこんでいるかのようだ。
木々のざわめきが、森を渡ってる。
「もうすぐ、最終便がくるよ」
と、音々が言った。わたしは、猫たちの方を見たまま、うなずいていた。
最終便が帰れば、明日の朝一番まで船はない。
そんなこと、考える必要もないほど明白だけれど、なぜだか動きたくなかった。
このまま、ゆったりとした時間の流れに身を委ねていたかった。
少しでも長く。
「急いで下りてけば、間に合うかもよ」
音々は、確認するようにそう言ったけど、彼女だってまるで立ち上がる様子も見せない。
大体、音々のやつ自分の足のことは忘れているんだろうか。
「いーんじゃない?」
別に音々に気を遺ったわけでもなく、わたしがそう言うと、そうだねって音々も言う。
――夜の帳が、わたしたちの上に優しく降りて来ていた。
不意に、後ろから音々が体を重ねてきて、わたしの頬に彼女のほっぺたをすり寄せてきた。
「なぁによ、暑苦しい」
わたしが両手で音々の体を押し退けると、音々はほっぺたを膨らませて不満そうな顔をする。
「なんでぇ? 猫の愛情表現なのに」
「わたしゃ、人間だい」
しっしって、しつこく寄ってくる音々を追い払う。
「でも、これが一番いいんだよ」
音々がすねたようにそう言った。
そう言うけど、人間の愛情表現だっていろいろあるんだけどな。まだ音々が知らないようなのも……
その時、わたしは面白い逆襲を思いついた。
「教えてあげようか、もっといい奴を」
すっ、と今度はわたしから音々の方に体を寄せる。
彼女のあごにそっと指をかける。音々が戸惑った顔をする。
「それはねえ……」
「? うん」
指を動かして、音々の顔をわずかに上向かせる。ちら、とだけ、わたしは草地の方に目を向ける。
(猫たちはちゃんと目を閉じててよね)
見ているのはお月様だけ。そんな夜だからこそ許されるジョーク。
「こうするの――」
唇を……重ねる。驚きに、音々が大きく目を瞠った。
(時間よ。もっと、ゆっくりゆっくり流れておくれ)
(けっして急くことなく)
(けれど留まりもせず)
(海にそそぐ大河のように、ただ、ただゆるやかに――)
END