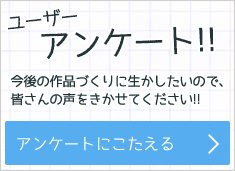1月も気がつけば19日。
もう一年が1/24終わったなんて考えたくない今日このごろ。
皆さん、風邪などひいてませんか?
インフルエンザ流行ってますので、注意してくださいね。
さて、ブログも三回目ですが、HPの方でまだキャラクタ-ボイスの公開も
済んでおらず、公開出来るネタも少ないので、
早速前回予告した「向坂氷緒先生の未公開 短編小説」を
公開したいと思います。
白愛とはまた違うテイストですが、先生の作家性は掴めるかも?
ちょっとブログで出すには長いので、全3回です。
向坂氷緒先生からコメントも貰っております。
「発売まで『白愛』を盛り上げねば!(目炎)」となってる宮澤さんに
「あのっ! デビュー前に書いた百合っぽい短編小説があるんで、
よかったら公式サイトの賑やかしにでも使ってください!(目炎)」と差し出したのが、この小説です。
デビュー前、作家志望者時代、まだ十代の頃・・・なので、ちらほら時代を感じさせる描写があったりします。
音楽をCDラジカセで聴いてたり、携帯電話がなかったり(時代だ!)、
ナップザックなんて、今使ってる子いるのかな。
宮澤さんにお送りする前に、ひさびさに読み返して、その若々しさというか、
青々しさというか痛々しさというか、そんなんに悶絶しました。
間違いなく、これは十代にしか書けない、それもちょっと〝こじらせた〟奴にしか書けない小説です(笑)
気楽に楽しんでもらえればと思います。
ではどうぞ!
「海にそそぐ大河のように」
Ⅰ
――家の中がやけにしんとしていた。
自室のある二階に上がろうと階段に足を乗せたところで、すぐとなりの居間から声がした。
わたしを呼んでいる。しかも、それは父の声だった。
家庭よりも仕事第一の父が、こんな早い時間に帰っているなんて珍しいことだ。
学校から帰ったばかりのわたしは、汗をかいた制服を早く着替えたかったので一旦部屋に戻ろうかと考える。
けれど、わずかに迷っただけで再び父に呼ばれて、そのままの恰好で居間に入っていった。
冷房が効きすぎの居間で、父と母が黒の革張りのソファに並んで座っている。
母はハンカチで目許を押さえ(泣いてる?)、父は不機嫌さを隠そうともせずに腕組みをしている。
そして、ガラスのテーブルの上に、三つ折りに畳まれたB5のリーフ。
カラーペンで書かれた、遺書という字を表にして。
父がここにいる理由がわかった。リーフを見つけた母が、父の職場に電話して泣きついたのだろう。
案外、父の不機嫌は仕事を邪魔されたせいかも、そう考えるとちょっとおかしい。
「わたしの引き出し、勝手に開けたんだ」
「そこに座りなさい、千歳(ちとせ)」
わたしの言葉に取り合わないで、父が言った。
逆らっても良かったけれど、それは得策でないと判断して、
わたしは鞄を床において素直に両親の向かいに座った。
「これはどういうことだ?」
父が、汚いものにでも触るような手つきで、リーフを摘み上げた。
三つ折りがパラリと開いて、父は視線で文面を撫ぜる。
わたしは、自分の裸を視姦されているような気がして全身に悪寒を覚えた。
「『死んでしまおうと思う』なんて何を考えているんだ、おまえは」
父が、最後の一文に目を止めたまま言った。
「汚らわしい……っ」
母が嗚咽まじりにそんな呟きをもらす。
――それは違うよ、お母さん。
このままずっと生きていって、心とか体に澱をいっぱい溜めこんで、
老いさらばえて死んじゃうってほうがずっと汚らわしいよ。
……やめた。
口に出して説明する気にはなれなかった。
どうしたって、二人には理解できない、ことなのだ。
「やっだなー。そんなの本気にしないでよぉ。冗談に決まってるじやない。じょーだんに」
努めて明るく言った。わたしの言葉に、父はまともに拍子抜けしたようだった。
母も、わけがわからないとでもいうように、充血させた目をわたしに向ける。
「……なんだ。嘘なのか?」
「嘘っていうかぁ」
わたしは困ったような苦笑いの表情をつくって答える。
「別に誰かをだまそうとか思ったわけじゃないし。
受験勉強で煮詰まってたときにちょっと気晴らし感覚で書いただけだもの」
「でも、そんなもの置いておくなんて! 親を不安にさせるようなこと……っ」
「そのうち捨てようと思ってたの! 勝手に引き出しを開けたのはお母さんじゃない。
いつもやめてって言ってるのに」
わたしは、強めの口調で切り返す。びくっとなった母に、調子を落として付け加える。
「でも、心配かけたのは、ごめんなさい」
親を言いくるめるなんて簡単だ。
ほんの少しの胸の痛みさえ我慢できれば。
落ち着いて安堵の表情を浮かべる母に、わたしは心の中で頭を下げた。
それからは、もうわたしのことから話題はそれて。
早合点して仕事を妨げた母を父が叱責し、それをきっかけに仕事第一の父と家庭のことを
全て押しつけられている母との口論が始まった。
そして、いつのまにか夫婦間の愛情へと問題が移り、論点が怪しくなってきた時点で、
わたしは受験勉強を口実に居間から抜け出した。
高校三年の七月といえば本腰を据えなきゃいけない時期。そこのところは両親もわかっているので、
咎められることはなかった。
肌に張り付いてくる、冷えた制服の嫌な感触に耐えるのはもう限界だった。
二階に上がったわたしは、着替えのTシャツとショートパンツを持って再び階下に降りていった。
手早く冷水のシャワーを浴びて着替えを済ませ、自分の部屋に戻ってさっぱりした体をベッドに投げ出す。
もう飽きてるんだけど入れかえるのも面倒なので入れっぱなしになっているCDをまたかけて、
忘れずに持ち出したリーフを眺める。
とくに考えなしに眺めていて、どれくらいの時間がたっただろう。
不意に、くらりと睡魔が襲ってきた。
疲れでも溜まっているのだろうか。溜まるような疲れなんて、遊び疲れくらいしか思いつかないけれど。
まだ日が沈みきってさえいないけど、なんだか眠れそうだった。
眠ってしまおう(勉強? TVドラマ? どうでもいい!)
リーフをカーペットに放り出して、CDラジカセのおやすみタイマーのボタンを押す。
早くも深い眠りに落ちていくまどろみの中で、死ぬときもこんな感じなのかなあ、だったらいいのになあ、
とわたしは考えている。
やっぱり、眠るように安らかな死ってのは理想だよね。
微かに父の声がした。
すごく遠くから聞こえてくるみたいだった。ドアの向こうから話しかけているんだろう。
本当になにも悩んでいないのか?
なにか嫌なことがあったなら、お父さんに言ってみなさい。
なにも悩んでなんかいないよ。嫌なことなんかなにもないよ。
毎日幸せだよ。幸せすぎて疲れちゃうくらい。
きっと、わたし、今人生で一番いい時期なんだよ。
もごもごと答えたので、ちゃんと父に聞こえたかはわからない。
そう、だからいつまでも、女子高生のままで……
* * *
「えー!? ちーちゃん、それ変だよ、変!」
……そーかなあ。
朝。同じ駅から学校に通っている音々(ねね)との、電車待ち時間潰しのおしゃべりの中で。
眠りに落ちるときって、あんまり気持ちいいからこのまま目が覚めなくてもいいやって思うこと、ない?
って聞いたその答えがこれだった。
音々ってのは、わたしの数多き友人の中でも抜きんでて変わった子で、だから、
その音々に変って言われたのは実は結構ショックだったりする。
まあ、わたしは音々のその変なところが好きで、一番の友人だと思っているんだけどね。
「けど、あたしちーちゃんのそんな変なとこ好きだよ」
音々がそんなことを言うもんだから、わたしは思わずプラットホームから
線路に落ちそうになった(ちょっと大げさか)。
おいおいって感じで、崩れた体勢のまま上目遣いに音々を見る。
きょとんとした、なんにも考えてませんっていう音々の顔。
わたしは、苦笑しつつ立ち直る。
変人コンビですか、わたしたちゃあ……
どしたのって音々が聞いてきたけど、わたしはべえっつにぃってとぼけてみせた。
変人コンビなんて言ったら、音々のことだ喜ぶだけに決まってる。
いや、それどころか、あちこちに言って回る可能性が大だ。
「――よかった。いつものちーちゃんだ」
音々が、安堵のようなため息とともにそんなことを言った。
いきなりなんで、わたしはただ音々の顔を見返す。
「……なによそれ」
「うん……。昨日ね、ちーちゃんのお母さんから電話あったんだ。
最近、ちーちゃん様子おかしくないですかって」
へえ、とわたし。まったく、うちの母ときたら、心配症なのやら、疑り深いのやら……
間違いなく、その両方だ。
「それで?」
「あたし、心当たりなんかなかったから、別におかしいところなんかないですよって言ったんだけどね」
そこで音々が口ごもるから、その先どういう会話がされたのか、母がなにを言ったのか、
わたしにはだいたいの見当がついてしまった。
「聞いたんだ。遺書のこと」
わたしの言葉に、うんって音々がうなずいて、それで、それからは二人して電車が来るまで黙ったままだった。
なんというか、あれはそもそもただ最近よく思うことを適当に書いただけで。
それが、たまたま結論として死んでしまうのがいいんじやないかってなったから、
親に言った言葉じやないけど遊び半分で遺書って書いただけなのだ。
けど、それを音々に言っても仕方がないだろう。
プラットホームに入ってきた電車がゆっくりと止まる。
わたしと音々は一番前に並んでいるので、後ろの人から押されてドアに押しつけられないように
踏ん張らないといけない。
厳かに(笑)、ドアが開くと、それこそいっせいに車内に人が雪崩れ込んでいく。
最前列にいたわたしたちとて、気を抜けぱもみくちゃにされて席に座れないということは十分にありうる。
しかし、そこは通学のプロ、女子高生をなめてはいけない。
わたしと音々は、しっかりいつもの座席を確保していた。
「いっつも思うんだけど、楽しそうねあんた」
となりでニコニコしている音々に、わたしはあきれた口調になる。
椅子取りゲームじやないんだぜえって感じだが、音々にとっては同じなのかも知れない。
「人間ってさ、毎日楽しいねえ」
なんて、音々はニコニコしたまま。心の底から思っているように言う。
「あたし、やっぱり人間に生まれ変われて良かったなあって思っちゃうよ」
「これが?」
わずらわしく眼前に迫るサラリーマンの中年太りの腹を、わたしはこっそり指さす。
「離れ島で、猫やってるってのも楽しそうだけど」
わたしには向かないけど音々には似合ってるよって続けかけて。
似合うもなにも、音々は自分の前世がそうだったって信じているんだから言ってもしょうがないのだった。
まあね、なんて急にたそがれた顔をして、ぽつりと音々が呟いた。
「でも、いいことばっかりじゃないから」
くるくる表情が変わって、音々を見ていると、この子本当に前世が猫だったんじゃないかって思えてくる。
「――ちーちゃんさ」
「ん?」
「遺書書くって、死んじゃいたいって思ってるの?」
わたしのほうを見ないで音々が言った。
わたしが、いつものような調子なので切り出しにくかったんだろう。
まーね、とわたしがなんでもないように答えると、音々は弾かれたようにこっちを向いた。
悲愴な顔で、なんでって聞いてきたけど、わたしは説明したものかどうかうーん、と悩んでみせる。
重ねるように、なんでって聞いてきたから、わたしは仕方なく答えることにした。
「だからさ、何か悩んでるとか、嫌なことがあってとか、そういうことじゃないんだよね」
音々は、頭の回りに「?」を飛ばして、いきなり脳味噌にパニックを起こしかけてる。
「いつだったか、みんなで言ってたじゃない。いつまでも女子高生でいれたらいいねって」
みんな、いっつも言ってるよ。音々の言葉にわたしはうなずく。
そうなんだよね。じゃあ、何でみんなそんなことを言うんだと思う?
え、えーっと、今が楽しいから? うん、それで半分は正解だよ。
半分? 音々がさっぱりわけが分かりませんって顔をした。
つまりさ、みんな知ってるんだよ。楽しい今がいつまでも続かないってことを。
だから言うんだ。いつまでも女子高生でいたいねって。
いつまでも女子高生ではいられないことを知っているから。
えー! そんなのって当り前だよぉ、なんて憤慨したように音々が言うから、わたしはなんでって聞き返した。
なんで、って……そんなの当り前じゃん!
当り前じゃないよっ。少なくともわたしは知ってるんだ。
時間を止めちゃう方法を。
「それが、自殺!?」
音々がいきなり大きな声を出すから、わたしはあわてて止めようとした。
けど、それは間に合わず、わたしと音々は満員の車内で視線の集中砲火を浴びることになった。赤面。
そして、注目を集めてしまったわたしと音々は、それ以上会話を続けることができなかったのだった。
学園前の駅までずっと。
* * *
駅から学校までは歩いて十分弱といったところだ。
電車から降り、改札を抜けて、校門まで続く緩やかな坂道をわたしと音々は並んで歩く。
まだ朝方だと言うのに、真昼のような日差しだった。
一旦途切れた会話というものは、なかなか復活しないものだ。
音々も、何かぎこちなさそうにわたしのとなりを歩いている。
思案して、わたしは前から一度音々に聞いてみたかったことを聞くことにした。
「音々ってさ。前世の、猫の記憶があるってことは、一度死んだ記憶があるってことだよね。
それって、どんな気分だった?」
聞いておきながら、わたしはまともな回答を期待していなかった。
結局のところ、わたしは前世なんてものを信じられるほどロマンチストではないから。
けれど、音々がどう答えるかということには興味があった。
音々が死に対してどんなイメージを持っているか、知りたかった。
「わかんない。死ぬときのことって、まだ思い出せないんだ」
なんて、音々はあっさりとそういった。
肩透かしをくらった感じだが、わたしは別に落胆もしなかった。
「夢に見るんだっけ?」
わたしの言葉に音々がうなずく。
うなずいてから、
「夢っていうか。寝てるときとか、起きてても本当にぼーっとしてるときとか、
ふっとこうずーっと忘れてた昔のことをぱっと思い出すみたいな、なんていうか、そんな感じなの」
音々は、音々の言葉で丁寧に説明してくれた、けど。
……よくわからない。
「死ぬときのこと」
「え?」
「思い出せたらちーちゃんに一番に教えてあげるよ」
と音々が言ってくれた。
わたしはちょっと考えて、「ありがと」とだけ答えた。
* * *
その日、一日中音々はどこかおかしかった。
わたしが、何かあったなと思ったのは二限目の授業の時。
つまらない古典なんてと、音々は授業開始と同時に睡眠体勢に入っていた。
わたしはといえば、知っての通り昨日の早寝のおかげで(なんと夕飯も食べずに朝まで眠ってしまった)
寝ようにも眠れず、机に伏せて眠る音々を横目で見ながらうらやましく思っていた。
がばりと音々が体を起こしたのは、授業も終盤に差しかかろうかという頃のことだった。
わたしは、いつもなら耳にするだけで眠くなっていた教科書朗読を延々と聞かされてかなり参っていて、
すぐには音々の様子に気がつかなかった。
音々はわたしを見ていた。ぼーっとしているような、何かを思いつめているような、そんな目で。
周囲のクラスメートを驚かせたことにも気づいていないようだった。
それからは、音々は休み時間も昼食の時もなんだか変な様子で、
友人たちからもあれやこれやと気にされていた。
わたしは詮索が嫌いなので、帰宅の途中で音々と別れるときも何も聞かなかった。
けれど、気になってはいたので、夜中に音々から電話があったときは
あわてて母の手の中の受話器に飛びついてしまい、
逆に音々のほうからどうしたの? と言われてしまった。
どうしたのじゃないでしょぉ? 音々、あんた今日。あのさ、ちーちゃん、今週の日曜、暇?
わたしに最後までしゃべらさずに音々がそう聞いてきた。
え、日曜? 待ってよ。ちょっと、説。ねえ、どうなのっ?なんて音々は重ねるように聞いてくる。
彼女、何だかやけに興奮してるみたい。日曜は、特に何もなかったはずだ。
一応、暇、だけど? ってわたしは答えた。じゃぁさ、つきあってくれないかな。
は? 何に。離れ島だよ。離れ島に行くの!へ? わたしは思わず間抜けな声を出してしまった。
離れ島って、音々が前世で生きてたっていう、あの?
なにしに? と、わたしが聞くと、音々は――あたしを探しにだよっ!
……。
わたしが黙っちゃったので、音々は、ゆっくり繰り返して言った。
そして、わたしはそれを夢のように聞いていた。
――だからね。あたしの死体を探しにだよ――
Ⅱへ続く。