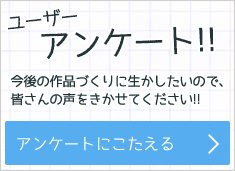公式HPで公開してる諸々、こちらのブログで触れてないのですが、
もしかしたらHP経由でなく、ちょくでこちらを見られる方もいるかもなので、
告知的な事もしつつでー。
「カスタムアイコンキャンペーン 開催中です!」
http://hakuai.kogado.com/special/
「CV当てクイズ 開催中です!」
http://hakuai.kogado.com/cp-cv/
という事で、向坂氷緒先生の短編小説第二回です!
どうなるんでしょうね(´∀`*)ウフフ
「海にそそぐ大河のように」
Ⅱ
渡し船が、対岸の臨海公園に戻っていく。
船着き場に立っているわたしは、することもなくそれをぼうっと眺めている。
音々は、わたしの隣でしゃがみこんでこの島の地図と格闘している最中だ。
一応、目的地は山の中のお堂ということらしいんだけど。
同じ船に乗っていた他の客たちは皆海水浴が目的なのでさっさと砂浜のほうに行ってしまい、
船着き場にはわたしと音々だけが残っている。
「やっと分かったーっ!」
いきなり大きな声を出して、音々が飛び上がるように立ち上がった。
「よぉっし。ちーちゃん、まずは村のあったところに行ってみよっか?」
音々がはりきった声を出した。
投げやりな声で、わたしはどーぞ御自由に、と答える。
ちーちゃんも行くの! とか言って、音々はわたしを引き摺るようにして歩き出す。
ここだけの話、わたしのナップザックには密かに水着などの海水浴用具一式が入っているのだ。
そして、音々が行くのは砂浜とはまるで反対の方向。
わたしは、青い海と白い砂浜の見事なコントラストを名残惜しくちらちら振り返りながら、
手を引っ張られるまま音々についていった。
引っ張られる。引っ張られる。……。
「……ち、ちょぉぉっと! 分かった、分かったから手、放してよっ」
観念したようにわたしが嘆願すると、音々は立ち止まってわたしに向き直り、手を放してくれた。
すでに、砂浜は小さくしか見えない。
「約束したのに!」
音々は、ほっぺたを膨らませてわたしを見ている。
「ごめん、ごめん。ちょっと、あんまり現実感沸かなくってさ」
これは本音だ。
死体探し、それも音々みたいに自分の前世の死体を現世の自分が探しに行くなんて、聞いたことがない。
それに、離れ島って言うと、わたしなんかは逢か南の熱帯の島とかを想像してしまうのだ。
それが、県内の臨海公園から一日九便も渡し船が出ている片道十五分のお手軽な遊覧の島だった、
なんて、なにかこう、歯車が噛み合わないんである。
けれど、わたしが謝ると音々はすぐに機嫌を直してくれた。
島を周り込むように弧を描く海ぞいの道を、わたしと音々は並んで歩く。
音々は、道に沿ってのびている防波堤の上を危なげなく、軽やかにステップでも踏むように歩いている。
小さく、なにか歌を口ずさんでいるようだった。
よく聞き取れない。でも、わたしもそれを知ってるような気が、する。歌うのをやめて、音々が言った。
「どうせなら、線路の上歩きたかったよねぇ」
「ああ、スタンド・バイ・ミー?」
そーだよって音々が返してきた。
そういえばあの映画も友人同士で死体探しに出るって話だったっけ。
けど、怪しさならこっちも負けちゃいない。なんせ、オカルトだ。
心の中で思っただけのつもりなのに、それが聞こえたみたいに音々がけたけたと笑い声を上げた。
口から、呟きになって洩れたらしい。
「――見えた!」
どこか緊張したような声を音々は出して、道の先を指さした。
わたしにも、道に沿って何軒かの家が並んでいるのが見える。
音々が聞いたところによると、島の唯一の村は何年か前に廃村になってしまったと言う話だ。
会いたいおばさんがいたんだけどね、と音々は言っていた。
会う方法がないわけじゃないんじゃないってわたしの言葉に、
なぜだか寂しそうに笑うだけだったな。彼女。
村に近づくにつれて、わたしには何となくその理由が分かるような気がした。
はっきり説明するのは難しいんだけど、音々が会いたかったのはおばさんという個人だけじゃなくて、
おばさんがいるということも含めてのこの村の風景だったんじゃないかな、ということだ。
あの晩、音々から電話をもらってから、わたしはふと音々が猫の生まれ変わりだということを
とても自然に受け入れている自分に気づくときがある。
例えば、今もそうだ。
けれど、かまわないんじゃないかと今では考えている。
こんなふうに流されてみるのも、悪くない。
この島についてから、そんな気分がいっそう強まってる。
防波堤から下りて、わたしより数歩先を早足気味に歩いていた音々が足を止めた。
一件の家の前だ。木造の、見るからに古い建物だった。捨てられてからは当然手入れもされていないはずで、
だからいつ倒壊しても不思議じゃないという感じだった。
ここが、そのおばさんの家だったのだろうか。
「あたしね――」
家の方を見たままで、音々がわたしに何か言おうとした。
その時、始終わたしたちの体を撫ぜている潮風に乗って、奇妙な音が聞こえてきた。
ちがう、これは音じゃない。これは、赤子の泣き声にも似ている――
「猫だ!」
音々にはすぐに分かったようだった。そうだ、これは猫の鳴き声。
視線を巡らせると、家のとなりに建ってる納屋のような小屋から一匹の猫――小猫が道に出てきた。
体全体が薄汚れてくすんだクリーム色をしていたけど、洗ってやればきれいな白の毛並みになりそうだ。
好奇心に満ちた目で――というのはわたしの推測でしかないんだけど――わたしたちを見ている。
わたしはてっきり、音々が駆け寄るとか呼びかけるとかするんじやないかと思ったのだけど、
彼女、小猫と視線の高さを合わせるようにその場にしゃがみこんだだけで、特に何をするでもない。
わたしも、何かできるわけでもないので黙ってそんな音々を見ているしかなかった。
音々がすっと手を差し出したのと、足を止めていた小猫が音々のもとに歩み寄ってきたのとが、
ほとんど同時だった。
わたしにはどちらが先に動いたのかまったく分からない。
胸の中に小猫を優しく抱いて、音々が立ち上がった。わたしの方に振り返る。
音々が、わたしの目をのぞき込むようにして言った。
「どしたの?」
え? 何が? 何を言われたのか分からず戸惑ったわたしに、音々は、
ちーちゃん変な顔してるなんて失礼なことを言ってくすくすと笑った。
変な顔? 何でだろ。
「この子、もしかしたらあたしの血、引いてるかも」
頭を捻っていたわたしは、音々の言葉に思わず、ええ!? と大きな声を出してしまった。
「何それ。その猫、音々の子供なの?」
「違うよお、たぶん孫だね」
「孫!? じゃあ、あんたお婆さんなんだ?」
言いながらも、わたしの頭はパニックを起こしている。
「孫がいるってことは子供を作ったことがあるってことだよね。
で、子供を作ったことがあるってことは相手もいたってことでしょう?
音々って、そうなんだ!?」
「ふつう順序逆じゃない?」
笑って言って、音々は頬を嘗めていた小猫を地面に下ろしてやった。
さして名残惜しそうな様子も見せずに、小猫は家の陰へと走り去っていった。
「あたしの旦那さん、おっきな灰色のぶちがある猫でさ。体もおっきかったな。ひねくれた性格しててね」
そう、懐かしそうに、音々は話し出す。
わたしたちは、防波堤にもたれて道に座り込んでいた。
日差しの具合でちょうど影ができているのだ。
「何で、その猫と結婚しちゃったの?」
猫同士の話に結婚というのもどうかと思ったけど、ほかにいい言葉も見つからなかったので、
わたしはそう聞いた。
結婚とか子供を作るとかって、わたしにはまるで現実感の沸かない言葉だ。
そーなんだよねえ、なんて音々は考え込む仕種。
「あいつ、ひどい奴でさ。ケンカはこの島で一番強かったんだけどね。
ボスって言うの? そんな感じ。……あたしこの島じゃマドンナだったんだよね。
真っ白の毛並みが自慢でさ。人間に飼われてたわけじゃないから保つのが大変でね。
求愛してくる猫ならいっぱいいたんだよね」
「じゃあ、何で?」
「発情期だよ。あたしの発情期の時にさ、ちょうどあいつと会っちゃってねぇ。
もう駄目、一瞬のうちに燃え上がりましたよ。これ以上はないってくらい」
「……ふうん」
「そういや、人間にはないの? 発情期って。それとも、あたしにまだなだけなのかな。ちーちゃん、どう?」
なんて、あっけらかんと音々が言う。
「ば。ばか! 人間にそんなのあるわけないじゃない!」
怒鳴るようにわたしは答えた。あー、顔が赤くなっちゃう。
へえ、そうなんだ。と、何でもないような顔をして、音々が話を続ける。
「でもね、猫には発情期って絶対なんだよね」
そこで、音々はなぜか沈んだ表情をした。
「――あいつさ、あたしと交尾がすんだらさっさとどこかへ行ってしまいやがんの」
こ、交尾、ですか。
……わたしゃあ、言葉を無くしちゃうよ。
「それからは、もう怒濤ですよ。子供も八匹もできてさ。
何とか守ろうとがんばるんだけど、結局は女の細腕でしょ。
どうにもならないことばっかりでさ……」
音々の言葉が途切れた。
涙ぐんでるのかな、と思ったけど。
わたしには、音々の顔をのぞき込むようなまねはできなかった。
大変だったんだ、ってわたしは、そんな言葉に何の効力もないこと分かっていたけど、でも、そう言った。
へへっなんて照れたように笑って、音々はわたしの方を見て「ありがと」と言ってくれた。
「もう、急流下りみたいな人生だったな。最期まで。……急流下りって知ってる?」
音々が聞いてきたけど、わたしは知らなかったので首を振った。
何でも、どこかの観光名物の一つで、流れの激しい川を船頭さんが
竿一本で操る小船に乗って下るというものなんだそうだ。
川の途中には、大きな岩とかもあって、なかなかにスリルがあるらしい。
音々の話に、わたしはふんふんとうなずく。
「んーと……女子高生の生活なんかは小川のせせらぎだよね。優しくって、可愛いいって感じ。
急流とどっちがいいかなんてあたしには分かんないけどさ」
そこで音々は口をつぐんだ。
女子高生の生活がどうとかいうのはきっとわたしに向けて言ったのだろうけど、わたしは何も答えなかった。
音々が、しゃべりすぎて喉が渇いたと、脇におろしたナップザックから水筒を取り出してる。
わたしは聞き手に回っていたのでそれほどでもなく、まぶしくない程度に空を眺めていた。
わたしはふと思いついて聞いた。
「会いたかったおばさんってのは?」
んー? と、音々が水筒に口をつけたままわたしを見た。
「ほら、言ってたじゃないよ」
「ああ。……あたしね、母乳がほとんどでなかったんだよね。
それで、一度子供連れて村に下りてきて、うろうろしてたらさ、
――くれたんだよね、おばさん」
「何、母乳?」
わたしが言うと、音々ったら声を上げておかしそうに笑ってる。
「なわけないじゃん。牛乳だよ。ミ・ル・ク」
あ、そりゃそうだ。わたしは自分の早とちりに気がついて恥ずかしくなる。
「そのおばさん、普段は超恐いんだよ。あたし、何回ほうきで追いかけられたかわかんないもん。
ミルクくれたときだって、全然優しい顔なんかしないでさ。あ、蔑まれてる! とか思ったね。
でもしょうがないじゃない? 子供たちみんな栄養足りてなくてさ」
……でも、今じゃ感謝してる。すっごく。そんなふうに、音々は呟いて、水筒の蓋をきゅっと閉めると、
そのおばさんに思いでも馳せるかのようにわずかの間だけど目を閉じた。
音々が目を開けるのを見計らって、わたしは言った。
「じゃ、行く? お堂ってとこに」
まさかわたしから言うとは思っていなかったのだろうか、音々は驚いたようにわたしの顔を見て、
それから嬉しそうに「うん!」と大きくうなずいた。
* * *
それを、わたしはすでにかなり後悔していた。
むせかえるような夏草の匂い。耳障りなセミの鳴き声。気が滅入りそうなほどどこまでも続く木また木。
……どれくらいの時間、歩いているんだろう。
十歩くらい先に、一心不乱に足を運ぶ音々の背中。
わたしはついていくのに必死だった。何度か、もうちょっとゆっくり歩いてくれるよう呼びかけたが、
まるで耳に届いた様子がない。
まるで、何か……わたしにはわからないなにかと対話している真っ最中のような。
息を切らせないためにも、わたしは黙ってついていくしかないのだけれど。
前を行く音々が、いきなり足を止めた。これさいわいとわたしが追いつくと、
わたしたちの前には橋が出現していた。
いや、橋は元からそこにあって、わたしたちが橋のあるところに辿り着いたというだけなんだけど、
変化のない風景を延々歩いてきたわたしには、その橋はまさに出現という感じに見えたのだ。
「あれ渡ったら、もうすぐだよ」
言って、音々は駆け出すように橋に足をかける。
ちょっと待て、とわたしは言おうとしたのだけど、息が切れて声が出ない。
その橋は、わたしでも一目で人が渡るのは危険だというのがわかるほど古いのだ。
音々のやつ、わからないのか!?
ストンと、音々の姿がわたしの視界から消えた。
橋を支えていた杭が、よほど腐っていたのかほとんど音も立てずに折れた。
縄もあっけなく引き千切れて宙に跳ねる。
膝の力が抜ける。
――胸が、苦しい。呼吸がとまる。
脳裏に最悪の想像がよぎる。
橋から下まではどれくらいの高さなんだろう。川があるなら水量は?
「音々!」
わたしは声を張り上げ、地面にへたり込んだまま、四つん這いで崖に近づいていった。
崖の下をのぞき込むように身を乗り出すと、川原に音々がうずくまっているのが見えた。
片方の足首を手で押さえている。
川原までは音々の背丈の倍ほどの高さがあったけど、崖が切り立ってなくて傾斜していたおかげで、
落下ということにはならなかったみたいだ。
川に落ちて流されてるということもなかった。
その点では、橋があまりにぼろかったことが幸運だったのかも知れない。
中ほどまで渡ったところで落ちていたらと考えると、ちょっと恐い想像だ。
うずくまったまま音々がなかなか起き上がらない。だから、わたしも崖を滑るようにして川原までおりていった。
がらがらと大きな音が立って、音々が気付いて顔を上げた。
「音々、大丈夫?」
わたしが心配して聞くと、よりによって音々の奴、足ひねっちゃったって恥ずかしそうに言ってから
「ごめんね」なんてすまなそうな顔。
音々が自力で靴と靴下を脱ぐと、その足首が一目見て分かるほど腫れ上がってる。
「ごめんね。これじゃ、もう行けないよね」
音々の言葉には、自分の足首のことと橋が落ちたことの両方が含まれている、とわたしは思った。
わたしが見たところ――なのであまりあてにはならないが――川の水深は、
浅いところを選んで渡れば膝頭くらいまでのところがありそうではあった。
しかし、それでも片足を痛めていてはとうてい渡れそうにない。
「ちーちゃんに、迷惑かけちゃったね」
音々がそんなことを言うもんだから、わたしの中で急速にイライラ度が高まりだしていた。めーわくだぁ?
「川の水で冷やしたら、痛み少しは引くと思うんだよね。ごめんね、ちょっと待っててくれる?」
どーやら音々は、わたしの不機嫌な様子を見て、理由を勘違いしやがってる。
ごそごそと四つん這いになって、音々は川に近寄っていく。その背中まで泥まみれで。
いい加減、わたしは怒鳴りつけてやろうかと口を開いた。
その時、わたしは視界のすみに――
「ちょ、ちょっと音々! あれ、あの猫!」
わたしが指さした川上の方向を音々も見る。
そこには、廃村にいたあのクリーム色の小猫がいた。
じっと、わたしたちを見ている。
わたしたちも二人して小猫を見つめていると、小猫は不意にくるりと反転して川上に向かって駆け出した。
と思うと、すぐに立ち止まって振り返り、またわたしたちをじっと見ている。
「ついてこいって言ってるのかな?」
わたしが聞いても、音々は答えず黙ったままだ。
小猫がまた、同じような行動をとった。
今度はわたしたちを見たまま「にゃー」と鳴いてみせる。
「あれ、絶対そうだよ。ついてこいって言ってるんだよ!」
興奮したようにわたしは言う。
まったく嘘みたいだけど、もう、わたしはとことん騙されてやろうと腹をくくっていた。
けど、音々は何だか乗り気ではない様子。
わたしが、川原に座り込んでる音々の顔をのぞき込むと、
「あたし、足が……」
ふうん。弱音、ですか。そーゆーものを吐くんですか。あんたがねー。ヘー。ほー。
「いーかげんにしろっての!」
ついに、わたしは容赦なく怒鳴りつけていた。
音々のまえにしゃがみこんで、柔らかいほっぺたを両手でつねる。
ぐにぐに手を動かしながらわたしは更に怒鳴った。
「あんたねえっ。迷惑なんて、これまでわたしに死ぬほどかけてるくせに、
何で今更しゅしょーな態度とろーとすんのよ?
じょーだんじやない。そんなので、これまでの迷惑代ちゃらにしようったってそーはいかないんだからね!」
(だいたい「友情」なんて相手に堂々と迷惑をかけるための大義名分なんだから。
こんなときにこそ振りかざすものでしょう?)
わたしが睨み付けてると、変な顔のまま音々が答えた。
「……ひょんなことひゃい」
「じゃ、ちょっと我慢しなさいよ」
えっ? て顔をしたかと思うと、音々は凄味をきかせたわたしにあわててかくかくうなずいてみせる。
わたしは川の水にナップザックから取り出したタオルを浸した。
すぐ歩くことを考えれば、靴とかは脱がないほうが正解だったんだろうけど、仕方がない。
わたしは、うろ覚えの保健体育の教科書の応急手当てのページを必死に思い出す。
濡れタオルをしぼり、わたしはぎこちない手つきで音々の足首を固定する。
「ほら、立って」
「うん……」
音々の腕を取って、一緒に立ち上がる。
足首が腫れてしまっているので履けない片方の靴を手にさげ、彼女の脇に体を半分入れて肩を貸す。
わたしたちが肩を組んで小猫のそばまで行くと、小猫は川上に向かって歩き出した。
わたしたちに気を遺っているように、ゆっくりとした早さで。
音々はといえば、今にも泣き出しそうな顔で、素直にわたしに身をまかせている。
「ちーちゃん、本気でつねるんだもん」
音々は、ほっぺたをさすって、痛かったあ……とつぶやく。
当たり前だよ、手加減なんかするわけないじゃん。
わたしはまだ怒ってるみたいに、ぶっきらぼうに言う。
怒りパワーは持続させないといけないのだ。
でないと、わたしのほうだってへたり込みそうなのである。
そして川上に向かって歩くこと十数分。
わたしたちは小猫に導かれ、その小猫でも簡単に渡れそうなほどの浅瀬に辿り着いた。
おかげで、わたしたちはあまり足もとの心配をする必要もなく、向こう岸に渡れたのだった。
向こう岸に渡ってからも、小猫はわたしたちを先導してくれるみたいだった。
わたしたちは橋のところまで下りていこうとしたのだけれど、
森へと入っていく獣道から小猫がしきりにわたしたちに向かって鳴くのだ。
どうするってわたしが聞くと、音々はついていってみようよと迷う様子もなく答えた。
目的地のお堂の場所を知っている音々がそう言うなら、わたしに拒む必然性はどこにもない。
それに小猫が行く道は獣道といっても十分に歩きやすそうであった。近道なのかな。
そして、小猫について歩くこと再び十数分。
いきなり森がひらけた。
Ⅲへ続く。